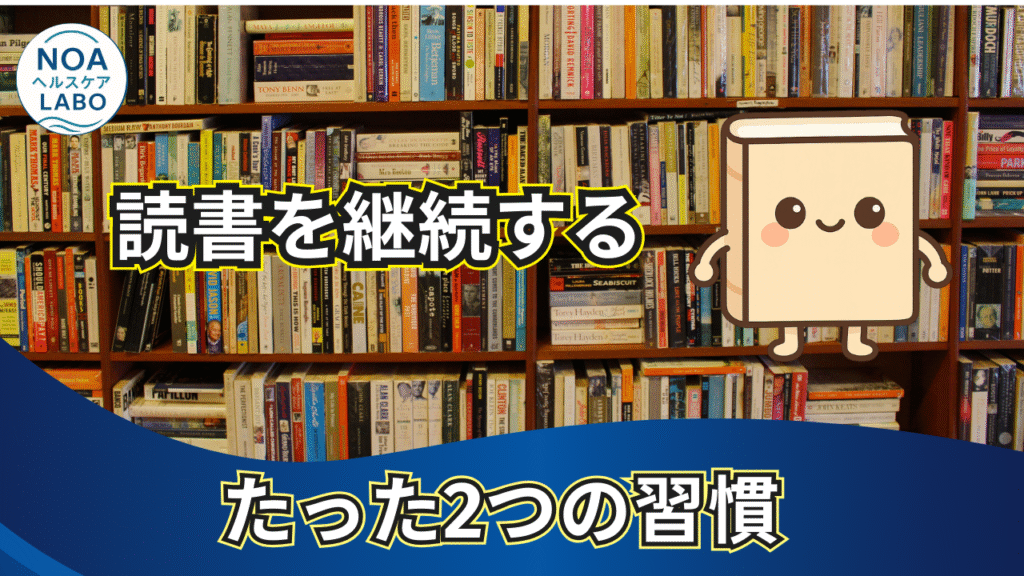
皆様は読書は好きでしょうか?
この記事をクリックしたという事は、「本を読むべきだとはわかっているが読書習慣が続かず悩んでいる」という事だと思います。
でもご安心ください、昨今本を読まない人が増えているそうです。かくいう私も、つい最近まで年間の読書数は0冊でした。
社会人なんだから本を読まないといけないといった義務感のようなものもあり、読む努力はしてみるものの、続かない。まさしく「三日坊主」の状態でした。
ただ今回お伝えする2つの習慣を取り入れると読書の習慣化の難易度は下がります。
最後までお付き合いください。
本記事の要約
読書を習慣にするのは意志の強さではなく、仕組みのつくり方です。
「習慣と組み合わせる」「スマホを遠ざける」この2つを続ければ、気がつけば1年で数十冊読める自分に変わっていきます。
なぜ本を読めないのか?
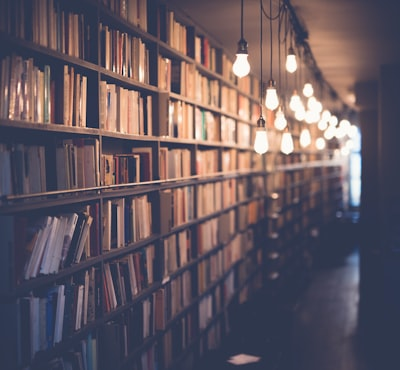
ケース1:スマホに集中力を奪われる
本を開いても、気がつけば手がスマホに伸びている。そんな経験はありませんか?
SNSや動画は一瞬で刺激や快感を与えてくれますが、本は数十ページ進んでやっと物語が動き出したり、知識がつながったりします。どうしても脳は「すぐに得られる快楽」を優先してしまい、集中が続きにくいのです。
さらに動画やショートコンテンツを見すぎると、脳は「速くて派手な情報」に慣れてしまいます。静かにページをめくる読書がどうしても“遅くて退屈”に感じられ、本に入り込めなくなってしまうのです。
ケース2:忙しくて時間がない
仕事に追われ、家事をこなし、一日が終わる。ベッドに入って本を開いても、数ページで眠気が来てしまう。そんな生活リズムの中では、読書にまとまった時間を確保するのは簡単ではありません。
しかも現代はスキマ時間すらスマホに奪われがちです。電車の中、昼休み、待ち時間……。本を読むはずの時間は、気づけばニュースやSNSで埋まってしまいます。その結果「読みたいけど読めない」状態が続き、本自体が生活から遠ざかっていきます。
ケース3:完璧主義で読めない
「最初から最後まできちんと読まなきゃ」
「理解できなかったら意味がない」
そんなふうに考えると、本を開くこと自体が重たくなります。途中でやめるのは失敗だと思い込み、結局最初の数ページで止まって積ん読が増えていく。これが完璧主義の罠です。
本来は飛ばし読みでもいいし、面白いところだけ読んでもいいのです。それでも知識や体験は必ず自分の中に残ります。しかし「きちんと読まなければ」と自分でハードルを上げすぎると、本を読むこと自体が苦痛になり、読書からどんどん遠ざかってしまうのです。
読書を習慣化する方法
方法1:既存の習慣と組み合わせる
新しい習慣をゼロから生み出すのは、とてもエネルギーがいります。だからこそ、すでに毎日繰り返している行動に「読書」をくっつけるのが効果的です。これは行動科学で「習慣の連結(ハビット・スタッキング)」と呼ばれる方法で、実際に習慣化の成功率を高めるといわれています。
通勤時間を「読書専用の時間」に変える
たとえば電車通勤。多くの人は習慣的にスマホを開いてSNSやニュースを見ますが、その時間を本に置き換えるだけで、1日30分前後の読書時間が確保できます。毎日の往復なら1週間で3〜4時間分、本に向き合える計算です。
ポイントは「通勤=本を読む時間」と固定してしまうこと。選択の余地を残さないほうが続きやすいのです。
夜のルーティンに組み込む
もう一つ効果的なのが寝る前です。歯を磨く、パジャマに着替える、ベッドに入る。この決まりきった流れの最後に「数ページ読む」を加えると、自然に“寝る前=読書”というセットが出来上がります。
大切なのは量ではなくリズムです。1ページだけでも構いません。「少しでも読まないと落ち着かない」状態に近づければ、習慣は定着します。
小さな積み重ねが「読書体質」をつくる
読書は一気に何十ページも読む必要はありません。むしろ毎日の生活の中で「少しだけ」繰り返すほうが長続きします。すでにある行動に寄り添わせることで、本を読むことが特別な作業ではなく、日常の延長に変わるのです。
習慣は意志ではなく仕組みで決まります。既存の習慣と組み合わせれば、無理なく読書が生活に溶け込み、気がつけば自然と「読書する人」になっていきます。
方法2:スマホを遠ざける
本を読むときに最大の敵になるのは「誘惑に負ける自分」ではありません。机の上に置かれたスマホそのものです。人間は目に入るものに無意識で注意を奪われます。たとえ通知が鳴っていなくても、視界にスマホがあるだけで脳は「確認したい」という衝動を起こし続けるのです。
意志ではなく環境を変える
「スマホを見ないように我慢する」という方法は、実は非常に消耗します。心理学では「自制心は有限」だと言われており、強い意思で抗おうとしても長くは続きません。むしろ重要なのは「意志を使わなくても済む環境をつくる」ことです。
例えば、
- 別の部屋に置く:視界から完全に消すだけで、衝動は大きく減ります。
- 引き出しにしまう:手に取る動作にワンクッション加えるだけでも効果があります。
- タイムロッキングコンテナに入れる:一定時間は物理的に取り出せないため、「少しだけ見たい」がそもそも不可能になります。
この「物理的に遠ざける」という環境調整は、読書の集中力を守るための最も強力な手段です。
スマホ依存の仕組みを逆利用する
スマホは「短時間で強い報酬が得られる」ように設計されています。SNSの通知や動画のサムネイルは脳の報酬系を刺激し続け、読書のようにじっくり時間をかける活動を不利にします。
しかし、これを逆に利用することもできます。たとえば、
- 読書の前に通知をすべてオフにする
- アプリをアンインストールして“すぐに見られない”状態にする
- 時間制限アプリを使って夜は自動的にロックする
こうすることで「スマホを見る快楽」より「本を読む以外にやることがない」という状況を生み出せます。
読書を優先できる空間をつくる
環境を変えるのはスマホを遠ざけるだけではありません。読書のための“専用の場所”を決めてしまうのも有効です。たとえば、寝室はベッド横に本だけを置く、リビングの一角に本用の椅子をつくるなど。そこにスマホを持ち込まないルールをつくれば、「その場所=読書モード」と脳が学習していきます。
「少し遠ざける」でも効果がある
大切なのは完璧に遮断することではなく、「ちょっと不便にする」ことです。手を伸ばせばすぐ届く位置にあると、無意識に触ってしまいます。けれども、立ち上がって取りに行かないと触れない距離にあるだけで、その衝動はかなり減ります。
まとめ
本を読めない理由は、スマホに集中を奪われること、忙しさで時間が取れないこと、完璧主義でハードルを上げすぎてしまうことなど、人それぞれです。大切なのは「自分の意思が弱いから」ではなく「環境や考え方が原因だ」と理解することです。
その上で、今回紹介した「既存の習慣と組み合わせる」「スマホを遠ざける」という2つを取り入れると、驚くほど自然に読書が続けられるようになります。毎日の小さな積み重ねが、やがて年間48冊以上という大きな成果につながります。
読書は特別な才能がなくても、誰でも習慣化できます。意志ではなく仕組みを整えることから始めてみてください。

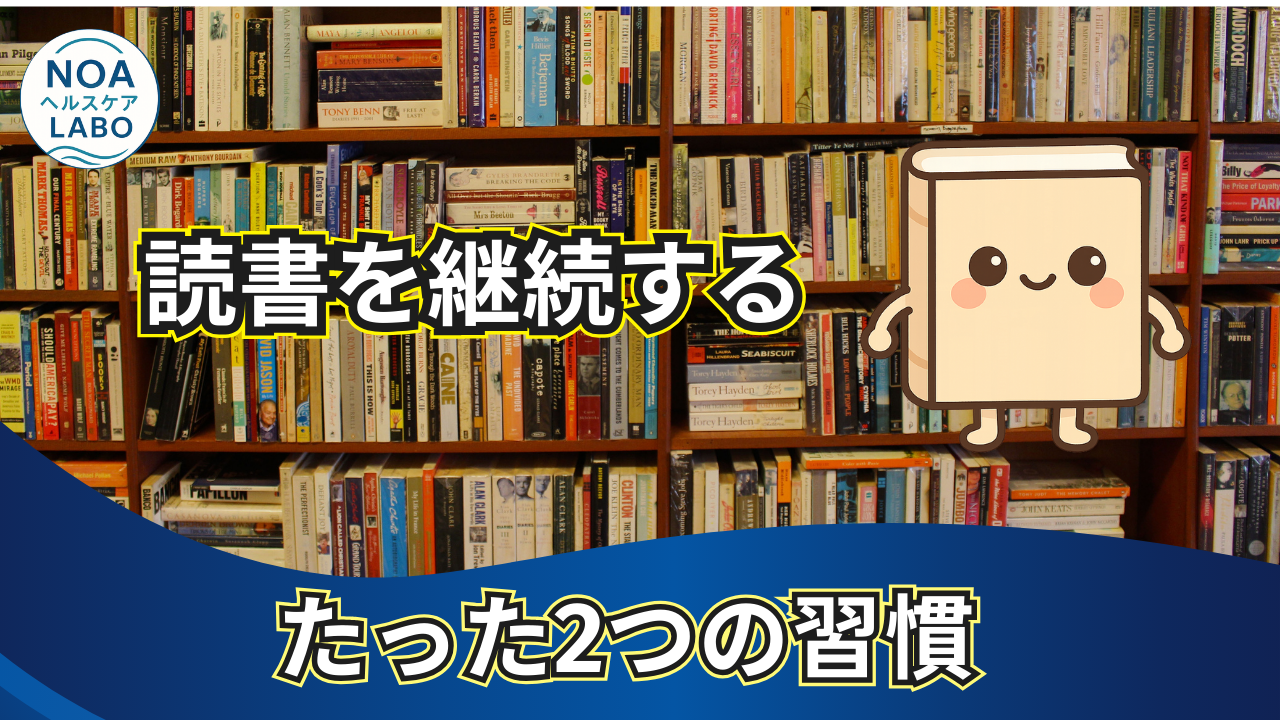
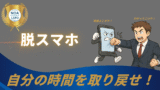
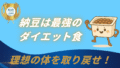
コメント